Recruit Blog リクルートブログ
【広島事務所】試験勉強と実務のギャップ
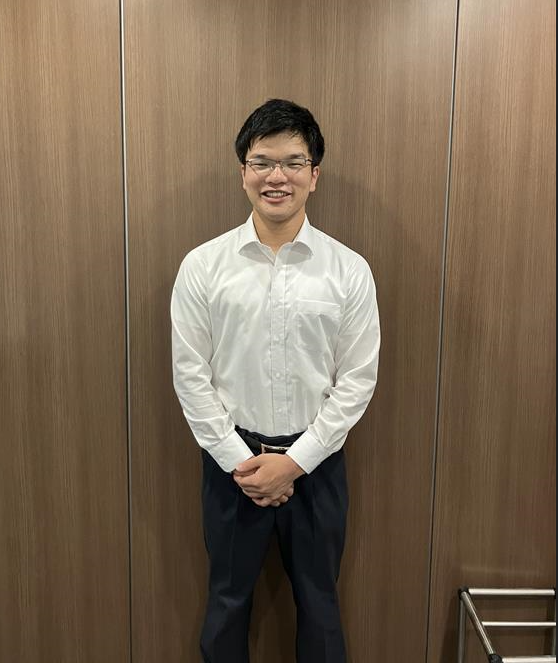
こんにちは!
入社1年目スタッフの小勝負(こしょうぶ)です。
まずは論文式試験お疲れ様でした!今はゆっくりと体を休めつつも合格後の仕事や私生活についてイメージを膨らませていることかなと思います。そこで今回は「勉強と実務のギャップ」をテーマに私が実務や先輩方の話を通して感じてきたことについてお話しします。
これまでの試験勉強で学んできたものは専門的知識であり、実務に沿った理論であるため実務でも生かされます。しかし、実務において試験問題では考える必要のなかった対応が必要な場面が多くあり、そこに試験勉強と実務のギャップを感じています。具体的には、試験では解答に必要な資料が揃っており、正誤を判定できるような「合理的」「正当な理由」といったヒントが問題文に散りばめられていたと思いますが、一つ一つ結論を導出するのに必要な資料や判断材料を収集、検討する必要があるということです。
現在の業務
監査調書の作成にあたって必要な資料が入手済みの資料にあるのか、先輩に聞いたら分かるのか、はたまたそもそも未入手でクライアントに依頼しないといけないのかなど資料の入手までに壁があります。そして必要な資料が揃っていたとしても直接的に関係のない情報も多く含んでいることがあるためどれが必要な情報なのか、資料の中の情報のつながりはどうなっているのかなど本来の目的の検討に入るまでの準備段階に多くの時間と労力が必要であり難しさを感じています。
先輩方の監査調書
試験問題の中で当然のように見積り要素である将来キャッシュ・フロー、減損会計の蓋然性の判定基準、会計処理や表示方法の変更が行われた際の「正当な理由」の判断基準などが与えられています。しかし実務ではまずそれらの論点を明らかにすることや、会計処理や開示に影響を与える判断を伴う要素について一つ一つ検討する必要があり、どのような過程を経て導出、検討、文書化されているのかを先輩方の監査調書や話を通して知り、実務の大変さを感じました。
ここまで少し硬い内容となってしまいましたが、試験勉強では何気なく使っていた情報や言葉の表現が実務ではどのように対応されているのかを知れることは楽しさでもあります。試験勉強で学んだ知識や理論を土台として実務があるため、それらを比較しつながりやギャップを感じられることも専門職ならではの魅力だと感じています。
このブログで少しでも実務のイメージを持っていただけたら幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。
事務所一覧
カテゴリー
アーカイブ
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年2月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年2月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年2月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年5月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月




