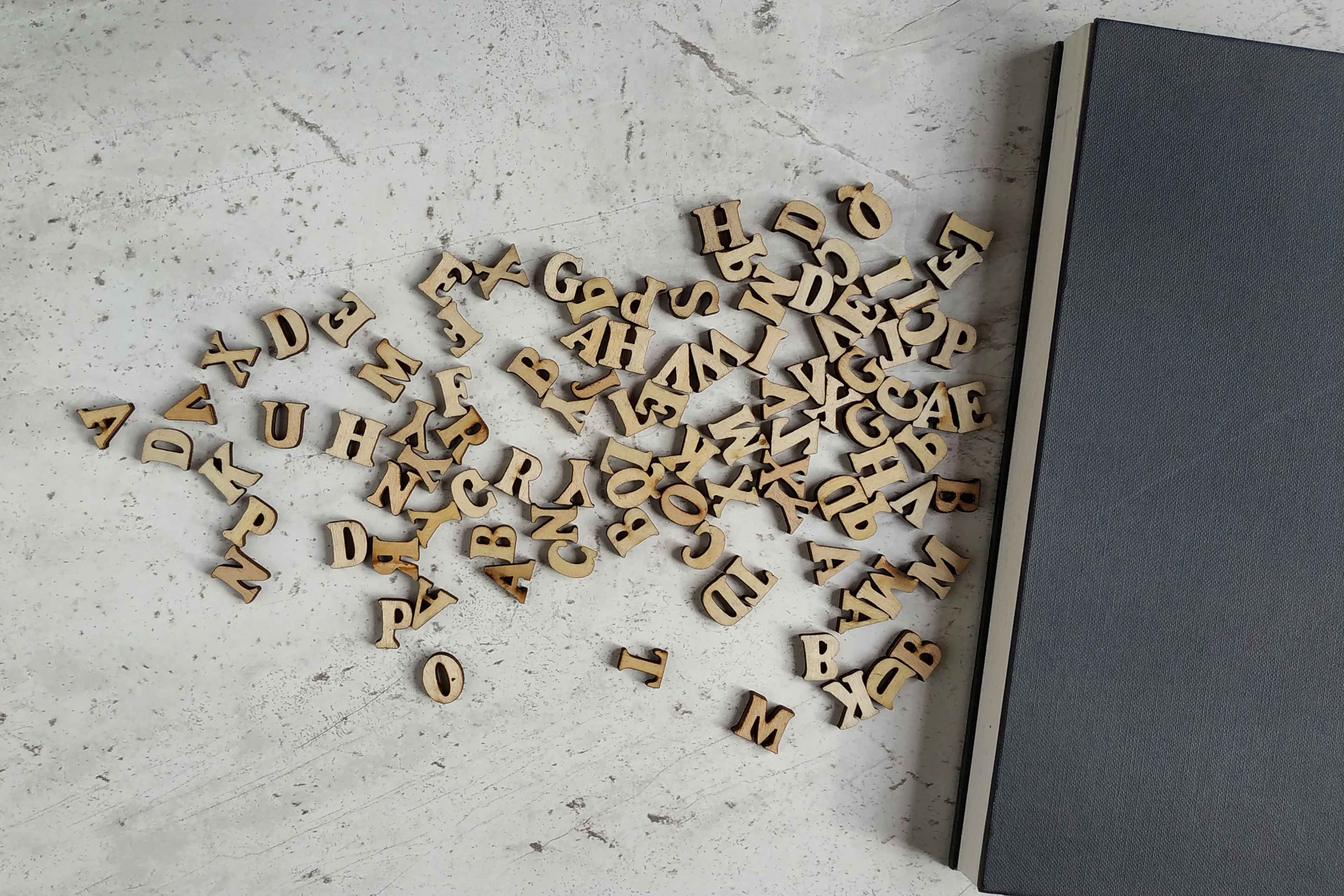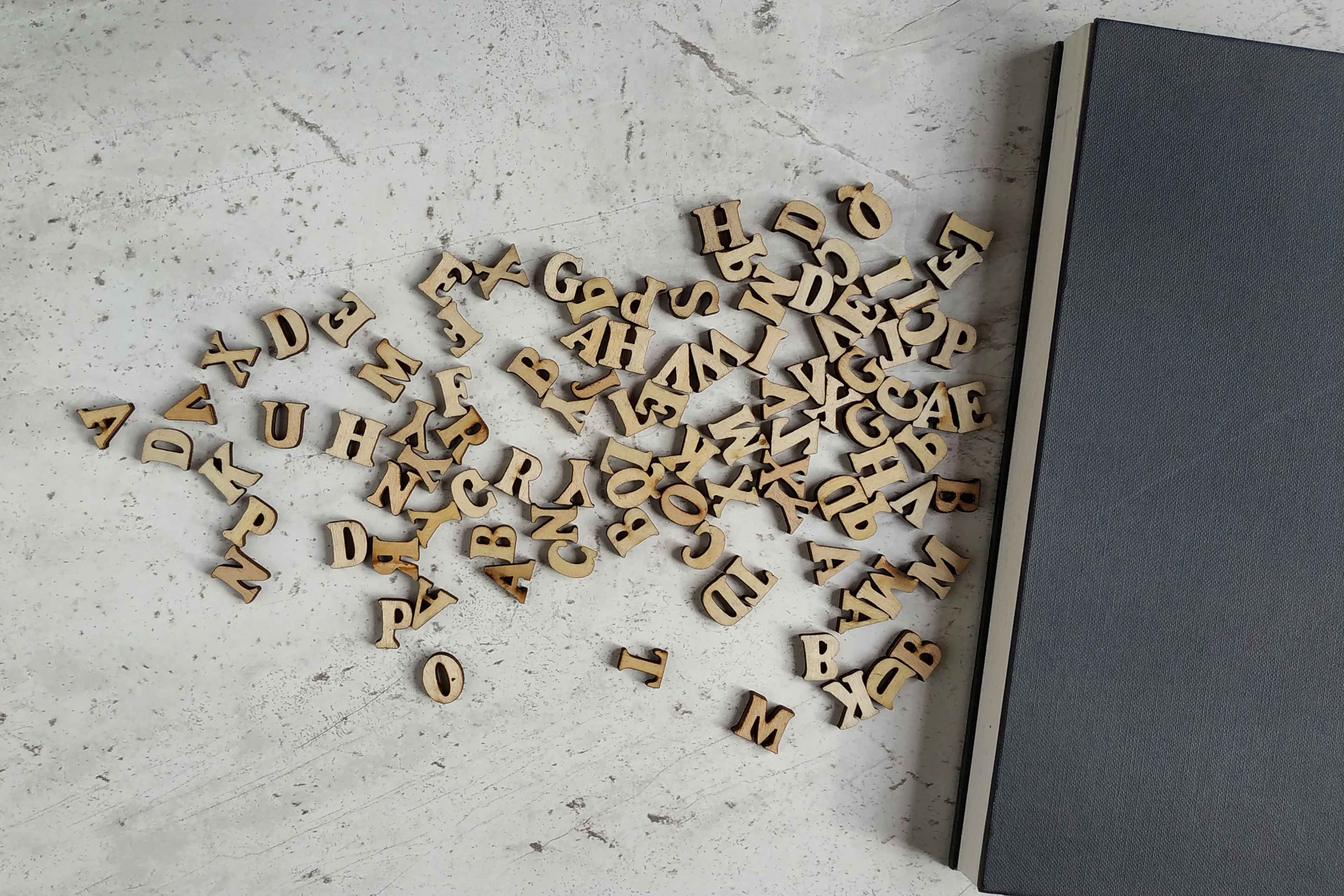EY.comへようこそ
本ウェブサイトを運用する上で不可欠なクッキーに加え、利用者の利便性とEYのサービス向上のために、次の種類のクッキーを使用しています。機能性クッキー:利用者の操作性を向上させるために使用します(例:選択した設定の記憶)。パフォーマンスクッキー:ウェブサイトのパフォーマンスを測定し、利用者のサイト上での利便性を向上させるために使用します。広告/ターゲティングクッキー:広告キャンペーンを行う第三者の広告サービス提供者により設定されるもので、利用者に関連性の高いコンテンツを提供することができます。
ブラウザーの「トラッキング拒否」設定が有効になっていることを確認したため、広告/ターゲティングクッキーは自動的に無効化されます。
クッキーの使用への同意は、ウェブサイトの各ページ下部にある「リーガル & プライバシー」から、いつでも取り消すことができます。
詳細はEYのクッキーポリシー(cookie policy)をご覧ください。
クッキーのカスタマイズ
任意のクッキーを使用しない