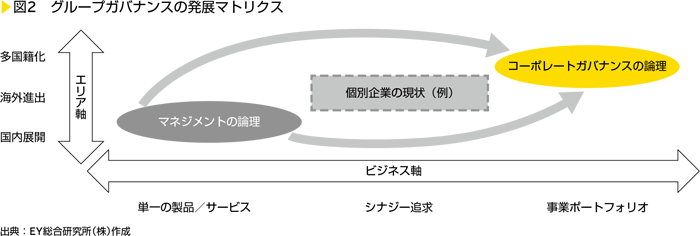グループガバナンスの手法とその発展-コーポレートガバナンスの論理とヒアリング調査による試論
情報センサー2016年11月号 EY Institute
EY総合研究所(株) 未来経営研究部 主席研究員 藤島裕三
1994年、慶應義塾大学大学院法学研究科修了後、同年に株式会社大和総研入社。企業調査部アナリスト、経営戦略研究部 主任研究員、企業経営コンサルティング部 副部長などを経て、2014年5月、EY総合研究所(株)入社。コーポレートガバナンス、IR、敵対的買収対応を専門分野とする。著書に『コーポレートガバナンス・マニュアル 第2版』(共著、中央経済社)、『Q&A コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップコード』(共著、第一法規)などがある。
Ⅰ グループガバナンスの必要性
2015年6月にコーポレートガバナンス・コードが適用開始されたことから、これに沿って多くの上場会社はコーポレートガバナンス強化に踏み出しています。独立した社外取締役の複数選任、指名報酬に関わる任意諮問委員会の設置、といった仕組みの整備が急速に進んでいることは、これまでのEY総合研究所(株)(以下、EY総研)による調査でも明らかになっています。しかし、このような株主・投資家を意識した仕組みを整えれば、企業のコーポレートガバナンス強化活動を推進したことになるのでしょうか。
コーポレートガバナンスの強化活動を実のあるものとするには、企業価値の創出につなげなければいけません。EY総研では、コーポレートガバナンスの論理を企業、さらにはグループの各階層において貫徹すること、すなわち「グループガバナンス」を構築することが有効だと考え、独自にヒアリング調査を実施しています。本稿では、有効なグループガバナンスの手法につき、コーポレートガバナンスの論理をベースに議論すると同時に、ヒアリング調査によって得られた示唆から、その在るべき姿について考察します。
ところで、コーポレートガバナンスとは、株主と経営者の関係を規律付けるものです。グループガバナンスはこれを応用した概念ですので、純粋持株会社における親会社(の経営者)と子会社(の経営者)の関係を想定すると分かりやすいでしょう。さらに社内カンパニー制や事業本部制についても、経営実態としては同様と位置付けることができると考えられます。以下、本稿では「グループガバナンス」について便宜上、親会社と子会社の関係を想定した用語で統一することにします。
Ⅱ グループガバナンスの手法(総論)
グループガバナンスの手法としては、役員兼任(人事)、実績評価(指標設定、報酬)、情報共有(会議体、報告)、そしてルール(内部統制)の四つが、一般に用いられています(<図1>参照)。これらの手法はほとんどの場合、企業組織の成長過程に応じて発展してきたと考えられ、その意味で「マネジメントの論理」で構築されていることが多いと推測されます。これらを「コーポレートガバナンスの論理」に従って再構築することで、企業価値を創出する目的にかなったグループガバナンスとなるというのが、本稿における仮説になります。
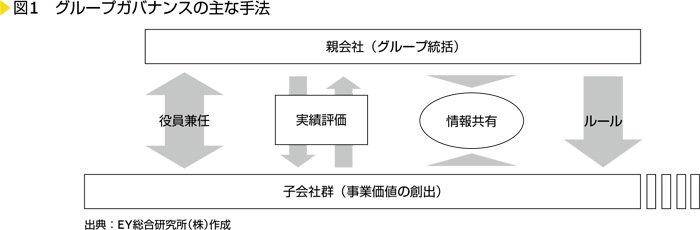
マネジメントの論理とは、経営者の雇用者に対するスタンス、極論すれば「上司と部下の関係」と言えるかもしれません。特に、わが国の企業では組織運営を円滑にするため、多分に属人的かつ情緒的な要素が占める傾向があるとされます。しかし、大規模なグループ組織においては、不透明な意思決定や非効率な業務執行の温床となり、事業環境の変化などに対応が遅れる可能性があります。
次に、コーポレートガバナンスの論理すなわち投資家の経営者に対するスタンスについて、その核となる主な概念とグループガバナンスの関連性を確認しておきます。
- 所有と経営の分離
上場会社の株主は原則として経営者に経営判断と業務執行を委ねており、企業経営に直接関与することはありません。グループガバナンスにおいても同様に、親会社は子会社に経営を一定の範囲で委ねることになりますが、役員兼任を通じて関与するケースがある点ではコーポレートガバナンスと異なることがあります。コーポレートガバナンスにおいて、株主は事業に精通していないことが前提となる一方、グループガバナンスにおける親会社の場合は相応の事業知識を有するのが通常、という違いが背景にあると考えられます。 - コーポレートファイナンスの観点
企業経営を委ねる以上、その成果を評価することが重要になります。コーポレートガバナンスでは上場会社の経営者の成果を、企業価値というコーポレートファイナンスの理論にのっとった、定量的な指標で測定することが求められます。経営を委ねる点ではグループガバナンスも同様であるため、子会社についてもその成果を評価することが重要です。グループ全体の企業価値との整合性に加え、評価プロセスの客観性確保のためにも、コーポレートファイナンスの観点を取り入れることが有効と考えられます。 - エンゲージメントの重視
前述の通り、コーポ―レートガバナンスにおいては企業経営を委ねた上で、その成果を事後的に測定するのが基本です。しかし、近年では株主と上場会社の対話、特に中長期的な方向性を議論するエンゲージメントが重視されるようになっています。グループガバナンスにおいても同様に、親会社と子会社が対話することを通じて、足元の情報共有だけでなく中長期的な経営の方向性についても、認識の共有を図るべきでしょう。
以上の問題意識について検討するため、EY総研では日本のグローバル企業約10社を対象に、グループガバナンスに関するヒアリング調査を実施しました。後述のⅢ 各論では、同調査で得られた各手法の実態について紹介し、コーポレートガバナンスの論理と突き合わせることで、若干の考察を導き出しています。なお、手法のうち「ルール」については、各社各様の風土や事業特性による部分が大きく、専らマネジメントの論理で構築されるものと考えられるため、本稿では、Ⅲ 各論の対象外とします。
Ⅲ グループガバナンスの手法(各論)
1. 役員兼任
親会社の役員が子会社の役員を兼任することで、各社がグループガバナンスに期待する目的・効果を実現しやすくなります。例えば、親会社でグループ全体の価値向上に責任を持つ立場の役員が子会社の経営トップを兼任していれば、グループ全体の価値を重視したシナジーの追求に意識が向きやすいでしょう。一方、特定の事業部門を所管する役員が兼任する場合には、子会社単独による企業価値の向上に注力しやすいかもしれません。子会社の自律的な経営判断および業務執行を優先すべき状況であれば、管理担当者もしくは非執行者(監査役など)による兼任にとどめる(あるいは兼任なしとする)べきだと考えられます。
【ヒアリングにより得られた実態】
相当程度に規模が拡大した企業グループにおいても、子会社に期待する役割や機能に整合した「適材適所」の配置よりも、グループ全体における人事ローテーションの一環といった位置付けを、役員兼任に求めているケースが見られます。このようなスタイルはグループの事業が多角化していない、または見かけ上は多角化していてもシナジーが大きい場合に有効な模様です。
一方でM&Aが活発な企業や、経営統合の経緯から複数のビジネスを抱えている企業では、親会社役員の派遣(兼任)に拘(こだわ)らないスタイルが目に付きます。これは子会社の自律性を最大限に高めると同時に、親会社が子会社を客観的に指導・評価するために一線を設けていると解釈することもできます。派遣する場合でも非常勤のことが多いようです。
なお、人事ローテーションのように役員を配置している企業でも、近年のグローバル展開に応じて現地人材に経営を任せる必要性が増えているようです。このような場合には、親会社から適材適所の役員派遣がなされることが散見されます。例えば、開発面のシナジーを期待して技術担当、コンプライアンスに懸念があるなら法務担当、などが挙げられます。
【EY総研による考察】
ビジネスが多角化していない企業においては、グループ一体型の経営でシナジーを最大化する観点から、親会社/子会社の別なく役員人事を行うことが有効です。しかし近年は、海外など展開するエリアの多様化から、人事政策に見直しが迫られるケースが増えているようです。その際には、ビジネスが多角化した企業のスタイルを折衷的に取り込むことが効果的でしょう。
2. 実績評価
グループ内で手掛けるビジネスや展開するエリアが多岐にわたっていると、親会社が全てを業務の詳細まで一元管理することは困難でしょう。そこで各子会社に個別の業績目標を設定した上で、その達成度によって評価(および報酬の決定)を行うことが考えられます。特に自律性の発揮を子会社に求める場合、このような管理は有効でしょう。一方でグループ全体でのシナジーを重視するならば、個別の子会社ベースではなくグループ全体最適の観点が、より強く求められることになります。
【ヒアリングにより得られた実態】
多角化したビジネスを事業ポートフォリオ的に統括している企業ほど、定量的な指標を設定しての子会社管理が徹底されています。このようなケースでは役員兼任に重きを置かず、子会社経営は買収前の経営陣や現地の人材などに委ねています。自律性を尊重した上で、厳しく成果を求めるスタンスと言えるでしょう。
これに対して、ビジネスが分散しておらず子会社にシナジーを求めるグループにおいては、厳格な業績評価に沿った子会社役員の報酬決定は、少なくとも積極的には行われていない模様です。子会社の事業戦略自体がグループ貢献を重視したものであること、グループ役員間のチームワークを高める必要があること、などが背景として挙げられます。
最もシナジーを重視する一体型のグループにおける指標管理についても、グローバル展開に応じて各エリアに固有の観点を織り込むなど、見直しが検討、そして試行されている模様です。現地人材の登用やグローバル人材の確保といった要請から、今後、報酬金額の引き上げも含めた子会社管理の再設計が、活発に実施されるものとみられます。
【EY総研による考察】
子会社評価(特に役員の報酬決定)については、経営トップの専権事項や人事の専管事項としてブラックボックスになっているケースも少なくないようです。それでも、グループ全体の一体感が強固であれば不満を抑えることもできますが、ビジネスやエリアが拡大して各子会社の自律性が高まると「見える化」が求められるのではないでしょうか。
3. 情報共有
(主に単体ベースでの)経営に関する意思決定や情報伝達は、業務執行役員の集まりである取締役会(あるいは常務会など)で事足りる、というのが従来の日本的な経営の在り方だったと言えます。しかし展開するビジネスやエリアが(連結経営の下で)拡大すると、あらゆるビジネスユニットやエリアの責任者を一堂に集めることは、親会社の取締役会では難しいでしょう。そこで、子会社の経営幹部にグループの方針を徹底させ、また各社の状況を共有するための仕組みとして、グループ横断的な会議体などを設置することが有効となります。
【ヒアリングにより得られた実態】
情報共有の会議体を活用する例は、グループガバナンスの在り方(シナジー重視か、分権経営か)にかかわらず、幅広く見られます。その一方で、役員兼任がグループガバナンスの基本となっており、必要に応じて親会社の経営トップと直接の対話をするため、仕組みとしての会議体は重視していない例も見られます。
ビジネスが多様化していない企業グループにおいては、シナジー(連携、クロスセルなど)を最大化するために、「ヨコ」の情報共有を促進する会議体が活用されています。その場における親会社の役割は、グループ戦略を推進する上で必要な情報を広く集約すると共に、各子会社が部分最適の事業戦略に走ることを戒める、というのが典型的です。
一方で複数のビジネスを展開する企業グループでは、子会社ごとの業績管理を精緻に行う必要上、「タテ」の情報共有を目的とする会議体が中心となっています。親会社からは個々の子会社に業績目標が与えられ、子会社からは同目標の達成状況につき報告されます。一定のグループ連携を図るため、親会社が主導して会議体を開催するケースも散見されますが、子会社主導で親会社はまとめ役に徹するケースなど、さまざまです。
【EY総研による考察】
特に「ヨコ」の情報共有を図る会議体については、グループ全体の意思決定や情報伝達を行う、いわば「拡大版マネジメント・ボード」と位置付けられるかもしれません。これはグループが拡大して参加者が増加するほど、回数や時間そして親会社の負担が増大するでしょう。一定の段階で「タテ」重視に移行することが合理的かもしれません。
Ⅳ グループガバナンスの発展
ヒアリング調査を総括すると、複数のビジネスが独立している企業グループにおいてはコーポレートガバナンスの論理に従ったグループガバナンスが構築されており、各ビジネスのシナジーを重視する企業グループについてはマネジメントの論理がグループガバナンスの基軸となっていることが分かりました。ただし後者に関しても、ビジネス展開するエリアの拡大に応じて、コーポレートガバナンスの論理が導入されつつあるようです。
以上から、グループガバナンスは企業グループが抱える多様性が拡大するに従い、コーポレートガバナンスの論理を強める方向で展開すると考えられます(<図2>参照)。バブル崩壊以降、わが国企業の多くは、選択と集中による事業再編を進めてきました。一方で、縮小する国内需要をカバーするため、M&Aなどを通じた海外展開が急ピッチで進められています。今後は特に事業のグローバル展開を成功させる観点から、コーポレートガバナンスの論理によるグループガバナンスの発展が必要とされるでしょう。